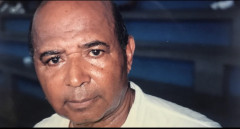日記
Fro Fro Fro de Jua
カポエイラ百科事典vol.19
Mestre Leopoldina
カポエイラの歴史には、
技やスタイルだけでは説明できない人物がいます。
今回紹介する、メストレ・レポルジーナも、その一人です。
⸻
カーニバルの土曜日に生まれた少年
メストレ・レポルジーナ
(本名:デメルヴァル・ロペス・デ・ラセルダ)は、
1933年、リオ・デ・ジャネイロで
カーニバルの土曜日に生まれました。
母親に育てられ、その後は叔母や近所の女性たちに世話をされながら成長します。
まだ幼い頃、彼は家を飛び出し、
リオ中心部と郊外を結ぶ中央ブラジル鉄道(セントラル線)周辺で、
列車に乗る子どもたちに飴玉を売って生活するようになります。
この頃の路上生活が、
彼の処世術や立ち振る舞いの基礎を形づくっていきました。
⸻
SAM(未成年者保護施設)での日々
十代の頃、極度の貧困の中で、
レポルジーナは自らの意思で
SAM(未成年者保護施設)に入ります。
恐れられていた施設でしたが、
彼自身はこの時期を否定的には語っていません。
水泳を学び、
施設のある島の周囲を日常的に泳ぎ回ることで、
彼は高い身体能力を身につけました。
路上で生きてきた経験は、
施設の中でも彼を自然と人の中心へと導き、
状況を読む力をさらに磨いていきます。
⸻
路上のカポエイラとの出会い
施設を出た後、
新聞売りとして生計を立て、やがて仲間をまとめる立場になります。
この頃、彼は
キンジーニョ(ジョアキン・フェリックス)と出会います。
キンジーニョは、
ビリンバウを使わないリオの裏社会のカポエイラ
「チリリカ」を操る人物でした。
この出会いが、
レポルジーナとカポエイラを結びつける最初のきっかけとなります。
⸻
バイーアのカポエイラとの接続
キンジーニョが獄中で殺害された後、
身の危険を感じたレポルジーナは一時姿を消します。
再び街に戻った彼が出会ったのが、
バイーア州イタブナから来た
アルトゥール・エミディオでした。
1954年頃、
レポルジーナは彼の弟子となり、
ビリンバウに合わせて行う
バイーアのカポエイラを学びます。
リオの路上で培った感覚と、
バイーアの形式が、
彼の身体の中で結びついていきました。
⸻
港、そしてサンバ・マンゲイラへ
港湾で働き、
港湾労働者組織に所属した後、
事故による早期退職を経て、
レポルジーナはより自由な生き方を選びます。
1961年、28歳のとき、
彼はサンバ学校マンゲイラのカーニバルに初参加します。
マンゲイラは、
カポエイラをパレードに取り入れた最初のサンバ学校でした。
レポルジーナは60人ものカポエイリスタを組織し、
カポエイラを祝祭の場へと導いていきます。
この関係は、1970年代半ばまで続きました。
⸻
メストレ・レポルジーナが残したもの
レポルジーナは、
多くを語る人物ではありませんでした。
しかし、
路上、施設、港、祝祭という場を生き抜いた彼の姿そのものが、
カポエイラのもう一つの歴史を今に伝えています。
Dende
Dendê o dendê
Dendê o dendê
Dendê é de angola
Angola é de dendê
Dendê o dendê
Dendê o dendê
Dendê é de angola
Angola é de dendê
Mestre pastinha
Foi embora
https://youtu.be/hDSgDAwQrxc?si=q30ad-iUalGn2szD
Tava na beira da praia Vendo o que a maré fazia,
Tava na beira da praia Vendo o que a maré fazia,
Quando eu ia ela voltava
E quando eu voltava ela ia.
Olha o nego, olha o nego
Olha o negoOlha o negoOlha o nego meu sinhôOlha lá o nego (nego sinhá)Olha lá o nego (nego sinhá)Olha lá o nego (nego sinhá)Olha lá o nego (nego sinhá)